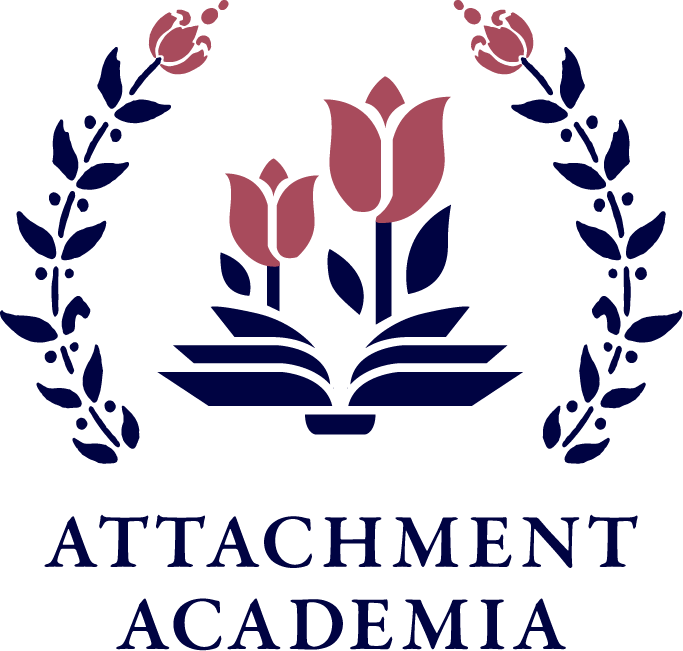社会にでたから、学びにもどる意義がある

アタッチメント・アカデミアは、
社会人が学びにもどるための
「大人の学校」です。
学校を卒業したあと、社会や現場を経験した人は、かならず仕事のなかで悩みや問題にぶつかります。そしていずれ、「このまま経験を積むだけでは前に進まない」という踊り場に立ちます。
それを乗り越えるためには、「知識とスキル」が必要となります。踊り場に立った人は、みなそう感じます。そこで成長する人は、この感覚にしたがって行動します。
“得られる学び”は人によって違う

そうして現場に動機づけされて、「学びなおす」という行動にでる人のために、当校は存在します。同じ講座を受講しても、受け手の状況や問題意識、あるいは経験や立場によって、“得られる学び”は全く変わります。別の言い方をすると、コンテンツ全体のなかから、どこを持ち帰り活用するかが違います。
たった一つか二つの“自分なりの学び”が得られれば、つぎのステージに進むことができます。
すべての学びは、
のちのステージで効力を発揮する

では、たくさんの時間を使って学んだその他の内容は、無駄になってしまうでしょうか?そんなことはありません。次のステージに進んだ後に、効力を発揮します。より広い知識、より深い知識を得ているからこそ、つぎのステージでは、何層も高いレイヤーの課題がたちあがります。
メタ認知による高揚感こそが、
勉強が楽しくなるメカニズム

この課題を乗り越えるために、また「知識とスキル」を学びにもどります。こんどは、前回とは違う景色がみえてきます。
これまでの現場での経験が積み重ねられ、いま新たに「学びなおす」と、前回学んだことと、今回学んでいることが、相互に反応して、より深い理解を生み出します。
メタ認知と呼ばれるこの脳の作用は、高揚感さえもたらします。
「勉強が楽しい」と思うメカニズムは、ここにあります。
人は、学び続けるように宿命づけられている

この繰り返しによって、人は成長してゆきます。このサイクルに終わりはありません。一生涯続けることができます。これは、人間という生物に課せられた宿命です。
哲学者パスカルは「人間は考える葦である」と言いました。学び続けることをやめない限り、人間は人間たり得るのです。
それをやめた瞬間、人間はただの葦になるのです。
“行動する人”と“行動しない人”

問題にぶつかって踊り場にたったとき、“行動する人”と“行動しない人”に分かれます。
前者は、踊り場に立ち行動するサイクルの数だけ、乗数的(2倍ではなく2乗)に成長が加速します。
問題をスルーして行動しない後者は、前に進まないまま時が流れて、また同じ問題が、形を変えて立ちはだかります。両者の違いを想像すると、パスカルの言葉の重みが実感できるというものです。
ただ学び続けることにも問題がある

一方で、「ずっと学び続ける」というのも問題があります。現場で『実践する』と問題にあたる。それを乗り越えるために『学びにもどる』。その学びをたずさえて、また現場で実践する…。
つまり、『実践』と『学び』は、対になって繰り返されるものなのです。
ずっと実践をつづけるだけでも、ずっと学び続けるだけでも、成長は得られません。
『実践』と『学び』のサイクルをまわす

アタッチメント・アカデミアは、『実践』と『学び』のサイクルをまわす人が集まる場であり、新たな学びを得る機会です。学びの必要性を感じたら、ここへ来て学んでください。学びを得たら、また現場にもどり実践してください。そして、必要になったときは、いつでも帰ってきてください。ここには、同じ志をもつ仲間がいます。必要な学びの機会があります。
ここには入学も卒業もありません。
『実践』と『学び』のサイクルは、一生続くものだから。
年齢も、職業や立場の違いも、何も関係ありません。
ただ実践し、ただ学ぶ、そして成長し続ける。
その営みのための場と機会を提供してまいります。
アタッチメントアカデミア
学長 廣島 大三