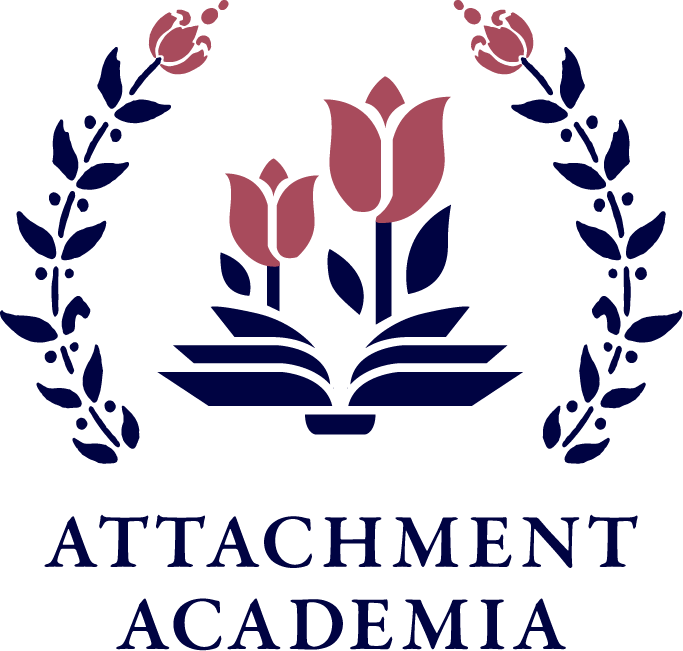日常体験と非日常体験

日常体験と非日常体験
一生もののアドバンテージを育てる体験教育とは?

アタッチメントが大事な0・1・2歳を過ぎて、3歳になったころ、子育ては教育を考えるフェーズになります。ここで言う教育とは、子育てに「体験」を取り入れることであるということは、前章でお伝えしたとおりです。つまり、親や教育者が考えなければならないのは、「体験」の機会の提供と、それにともなう「教育投資」という概念です。
つまり、エアレープニスとしての体験(本物の体験)を、意識的・意図的に子育てに取り入れて、体験に対する教育投資をおこない、非認知スキルの育ちを加速させ、一生もののアドバンテージを手に入れるということです。ここではこれを「体験教育」と定義しましょう。
毎日の「日常体験」の繰り返しによるエアレープニス(本物の体験)
体験の基本となるのは、「日常体験」です。いつもの毎日のなかで繰り返し起こる、固有の主観的な体験です。営みとしては同じことをしていても、「体験」として展開する固有の物語は、ひとつとして同じではありません。そうした体験こそが本物の体験であり、エアレープニスと呼ぶことができます。年齢が小さいほど、日常体験から発見したり学んだりする頻度は大きく、重要性も高まります。
日常の遊び、おしゃべり、散歩、食事、おふろ・・・子どもが日常で経験するすべてのことが「日常体験」であり、子どもの学びを導く体験です。子どものことをよく観察して、子どもの体験のなかの物語を聞いてあげることで、いつも変わらぬ日常が、体験教育として機能するようになります。子どもが、みずからの体験を言葉や絵で表現することは、ひとつの体験をエアレープニスへと昇華させてくれます。

この時期の「日常体験」は、安心・安全が前提です。お母さんや保育者が近くに居て関わってくれて、いつもの場所、いつものおもちゃ、いつもの営みを繰り返します。日常体験では、不安や恐怖は排除されなければなりません。
そうして積み重ねた「日常体験」は、子どもの中に自尊心と自信を育み、「なんだってできる!」という確信を育みます。これがのちに「非日常体験」とのシナジーを生み、能力の種を開花させ、非認知スキルを高めます。
ときどき訪れる「非日常体験」が、発達を加速する
次の段階の体験は、「非日常体験」です。いつもの日常の中には存在しない体験です。子どもにとって、非日常体験は予期せぬ未知の体験です。適度な不安や恐れをともなうこともあるでしょう。同時に、何が起こるかわからないというワクワクやドキドキもあるでしょう。
海や山の自然体験やキャンプ、都会の子の田舎暮らしなどがそれにあたります。また、クラフトなどの〇〇づくり体験とか、田植え体験、泥んこ遊びなどのアクティビティも非日常体験です。もっと身近なことで言えば、行ったことのない公園で遊ぶことや、家族旅行の旅先での行動も、これに当たります。

子どもは、日常体験のなかで積み重ねて獲得した能力や認知、感受性をもとに、非日常体験に挑み、ここでも独自の物語をつむぎます。この物語は、日常体験におけるそれよりもダイナミックで、刺激的で、壮大で、エキサイティングです。
非日常体験では、子どものことをよく観察して、子どもの体験のなかの物語を聞いてあげることが、より重要になります。物語のなかには、子どもの成長や発達、能力の開花した瞬間などが読み取れることでしょう。それを言葉にして、子どもに伝えてあげると、体験はより独自のかけがえのないものとなり、高度なエアレープニス的体験となります。
「教育投資」という視点から、体験の機会を与える
非日常体験の機会を与えてあげることによって、体験は、より高度に昇華され、認知や理解が深まったり、技術や能力が高まったり、洞察力や表現力、発想力、問題解決力を育みます。非認知スキルが高くなるというのは、そういうことを言います。
3歳から8歳は、「教育投資」という視点から、体験の機会を与えることが重要です。毎日の日常体験に加えて、非日常体験の機会を設けて、意識的・意図的に体験教育をほどこします。そうすることで、驚くほどの非認知スキルの高まりと能力獲得ができます。